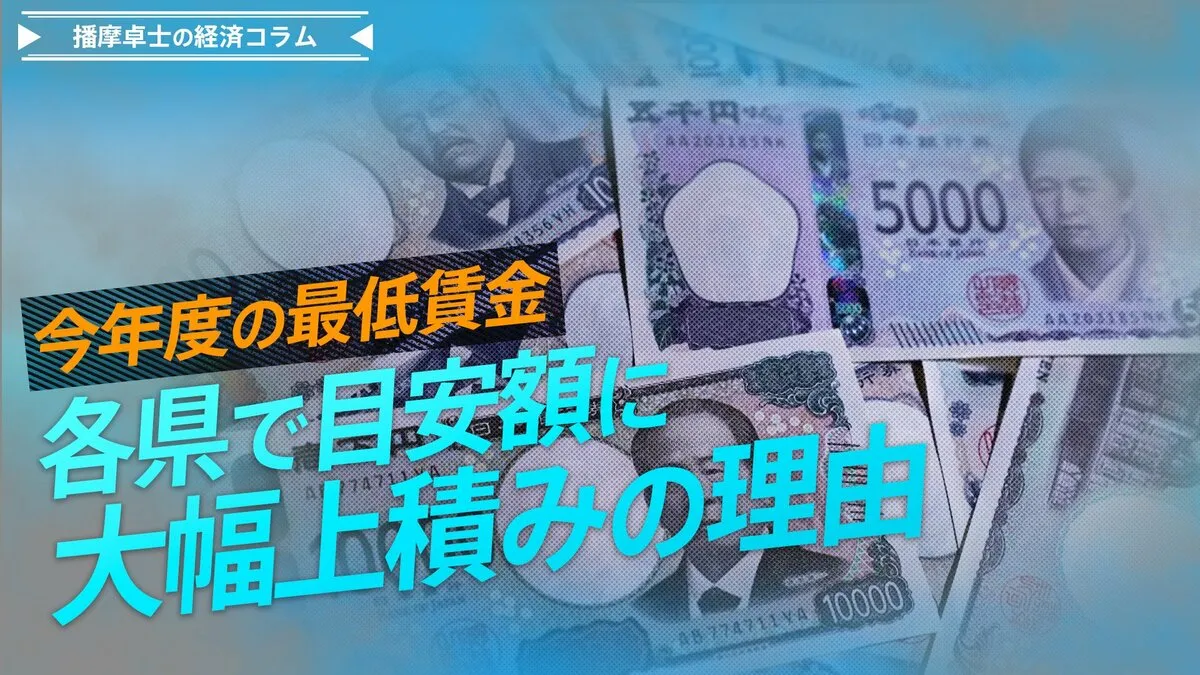
都道府県ごとに決まる、今年度の最低賃金が出揃いました。各地で国の目安額を大きく上回る決定が相次ぎました。来年の春闘に向け、賃上げのモメンタムが続くと期待する声がある一方、地方経済への逆効果を懸念する声も上がっています。
【画像解説】難航する地方の賃上げ 審議会では経営者側が全員退席する場面も...
国の審議会は過去最大の引き上げ提示
最低賃金は毎年夏に国の審議会が引き上げ額の目安を決め、それを受けて、各都道府県がそれぞれの最低賃金を決める仕組みになっています。今年は、8月4日に厚生労働省の審議会が25年度の最低賃金の目安を、全国の加重平均で63円、率にして6%引き上げて、時給1118円とすることを提示しました。目安の引き上げ幅は過去最大で、食料品を中心とした物価高や、「2020年代に時給1500円」という政府の目標にも配慮したものでした。
その上で審議会は、経済実態によって3つに分けられた全国各県について、賃金の低い秋田や沖縄などCランクの13県は64円、賃金の高いAランクの6都府県と、残りのBランク28道府県については、63円を引き上げ幅の目安としました。
最下位脱出に向け、秋田県80円上げ
これを受けて行われた各県での審議では、目安を大きく上回る決定が相次ぎました。最大の引き上げ幅となったのは熊本県で、目安の64円に18円も上積みし、82円の引き上げを決めました。次いで隣の大分県が81円の引き上げで決着。人手不足感が強まる中で、さながら近隣県との「最低賃金引き上げ競争」の様相を呈しました。
中でも、これまで時給951円と全国最下位だった秋田県は、8月下旬に早々と、16円上積みした80円もの引き上げを決め、各県に衝撃を与えました。なんとしても単独最下位からの脱出を、という秋田県の鈴木知事の要請も、異例の高い引き上げ決定の後押しになりました。
もっともあまりの引き上げ幅に、公的な事業者支援の準備が必要だとして、引き上げ実施を、通常の10月から、来年3月31日に先延ばしする異例の措置が取られました。
岩手県では経営側委員全員が退席
この決定に衝撃を受けたのが、お隣の岩手県です。岩手県は昨年は1円差で下から2番目、一昨年は全国最下位と、秋田県と競う間柄です。秋田県の決定から3日後、岩手県の審議会は79円引き上げて、秋田県と同じ1031円とすることを決めたのです。
どの県も「最低賃金の最低県」にはなりたくないものですが、岩手では、経営側委員5人全員が「強い反対」の意思を示すとして、退席する中で採決が行われました。その他の県でも、経営側委員が退席する例は発生しており、労働側、経営側、公益委員の3者が「十分話し合って決める」という、これまでの慣行が変質してきたことを表しています。
結局、国の目安を上回る引き上げを決めたのは、39道府県に及びました。今年度、秋田県に変わって最下位になったのは、沖縄、宮崎、高知の3県の1023円ですが、この3県も引き上げ幅は71円と、目安の64円に比べれば大幅です。これで、すべての県で最低賃金は1000円台を達成しました。全国加重平均も、当初の目安をさらに3円上回る1121円となりました。
昨年の徳島県84円引き上げが契機に
今回、各県によるいわば上積み競争の契機となったのは、昨年、徳島県が84円という破格の引き上げに踏み切ったことでした。徳島県の後藤田知事は、県独自の試算を行って「現行の最低賃金は、生産性など徳島県の経済実態からかけ離れている」と大幅引き上げの旗振り役を務めたのです。
徳島の場合は、大阪や神戸と橋と道路で繋がっていることから、最低賃金の大きな格差が人材流出につながっているという危機感も大きかったようです。これまでは、国の目安にせいぜい数円上積みするのがやっとだった各県が、一気に四国トップに躍り出た、昨年の徳島の「成功」に、大いに刺激されることになったのです。
都道府県が大幅引き上げに傾く理由
各地で大幅な最低賃金上積みが行われた第一の理由は、何といっても物価が上がっているという事実です。とりわけ食料品やエネルギーといった生活必需品の値上がりが大きく、最低賃金で働く人々には厳しい状況が続いています。国の審議会でも、食料品価格が6.4%も上昇していることが6%台引き上げの根拠となりました。
第二には、人口減少と慢性的な人手不足に対する地方の強い危機感があります。特に、近隣県との差が大きいと、人材が流出するという理屈です。
さらに、現在の決定方法では都道府県知事の意思が働きやすいというのも、理由にあげられます。どの知事も近隣県には対抗心がありますし、県民に賃金アップをアピールしたいという政治的動機もあるでしょう。その意味では、一連の決定劇は「最低賃金の合理的な決め方とは」という課題も投げかけた格好です。
最低賃金引き上げは必要
賃上げが大きな政策課題だと言っても、賃金は元来、民間企業が労使の話し合いで決めるものです。その中で、最低賃金は国が唯一、直接介入できる賃上げ政策と言えるでしょう。今年度の最低賃金が大幅な引き上げで決着したことは、賃上げ継続に向けた石破政権の強い意志を示したものであると同時に、地方の知事らもその方向性を共有していることを示しました。それは、いわゆる「賃金と物価の好循環」実現にも資するものです。
また最低賃金の決定、実施が、毎年の春闘の中間地点にあたることから、来年26年の春闘への勢いをつけるという点でも、大きな意義があったと言えるでしょう。
地方経済界からは逆効果との懸念も
その一方で、「急激な最低賃金の引き上げは、需要が弱い地方経済を逆に疲弊させることになる」と懸念する声も上がっています。賃上げのコストは、まずは価格転嫁によって吸収されるべきものですが、「地方でラーメンが一杯1500円になれば、客は来てくれない」といったことはよく聞かれる話です。
地方から都市部への人口流出についても、賃金格差が理由なのではなく、そもそも地方に仕事がないことが理由だと論理矛盾を指摘する人もいます。無理に最低賃金を引き上げると、廃業や倒産を通じて雇用が奪われ、一層、労働力が流出するという見方です。
頼みの綱であるはずの生産性向上についても、最低賃金引き上げに喘ぐ企業には、そもそも省力化などに投資する余裕がないという指摘もあります。
最低賃金の引き上げだけで、日本全体の賃上げや、まして経済の好循環が実現するわけでもありません。賃上げ継続への動きを評価しつつも、賃上げを可能にする成長のための、きめ細かな政策支援を続けることが求められています。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)
・“ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った! “何となく”で選んでいませんか?効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】
・「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク2か月後に新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」
・女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市

