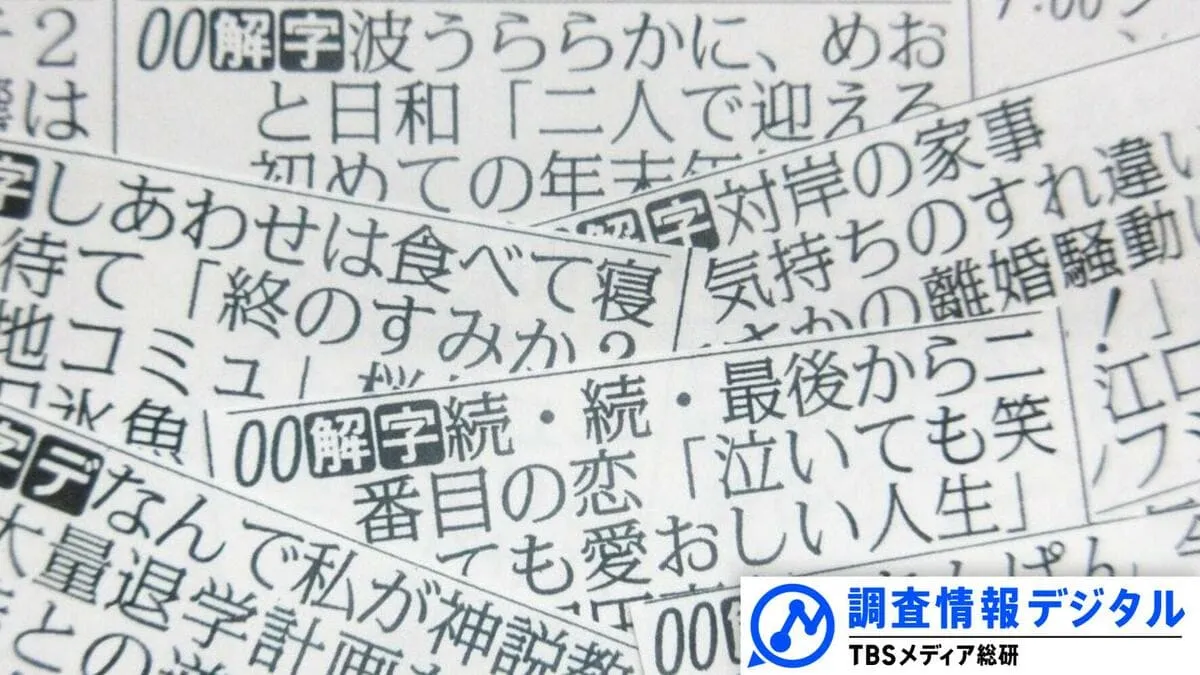
2025年4月期のドラマについて、メディア論を専門とする同志社女子大学・影山貴彦教授、ドラマに強いフリーライターの田幸和歌子氏、毎日新聞学芸部の倉田陶子芸能担当デスクの3名が熱く語る。様々なドラマを見てきたライターが驚いたドラマの結末と、視聴者のリアクションとは?
なぜ若者がハマった?「波うららかに」
影山 「波うららかに、めおと日和」(フジ)からいきましょう。
田幸 原作も読んでいたんですが、戦前の昭和を描いた作品を民放でドラマ化するのは新たな鉱脈だと思いました。民放でこの時代を扱う作品があまりなかったのは、視聴者にとって、ちょっと遠くて共感しづらいんじゃないかと制作側が考えていたのかもしれません。
しかしこの作品は多くの支持を得ました。なぜ受け入れられたかというと、そこには現代の恋愛ドラマを作る上での障壁がかかわっていると思います。携帯など便利なツールが登場して以来、恋人たちの「すれ違い」がなくなったことで、恋愛ドラマを作りにくくなったとはかねて言われてきました。そんな中、工夫しつつ他の障害をつくってきたのが最近の恋愛ドラマです。
そこで、じゃあ時代を変えて、携帯がない時代を描けばいいんだということになったわけですね。それが新鮮な恋愛の物語として若い人に響いた。私たちも昭和的な懐かしさを感じることができて、どちらの層にも受けた。
倉田 二人の関係がなかなか進まなくて、ヤキモキしながら見ていました。すれ違いがなくなったという話が出ましたが、すれ違うからこそ、今あの人は何をしているんだろう、何を考えているんだろうとか、いろいろな気持ちが生まれる。相手のことを考える時間は会えない分だけ増えるわけで、そういう時間を持つことへのあこがれが、見ている人にはあったのかもしれません。
田幸 結婚式には夫が仕事でいなくて写真だけ、そんなところからお互いを知って、好きになっていくすごくピュアな物語でした。夫は海軍なので、基本は家にいない。なかなか会えないからこそ、一緒に御飯を食べるという当たり前の日常の尊さが描かれる。それは、私たちがコロナの時に体験した、当たり前のことがいつできなくなるかわからない、会いたい人に会えなくなることがある、その記憶と重なり合います。
芳根京子さんがいいです。この作品のヒロインはあまりにも純粋で、恋愛や男の人のことを知らなすぎるキャラクターですよね。こういうヒロインは、うまくやらないと、わざとらしく、あざとく見えてしまうんですが、芳根さんがやると本当に嫌味がない。
影山 芳根さんは「明るい不器用さ」を表現させるとピカイチですね。ほっこりさせるというのか、それが本当にうまい。僕が彼女で一番好きなのは「チャンネルはそのまま!」(北海道テレビ・2019/2020、新人テレビマンの奮闘記)です。明るい不器用さそのままで、彼女の持ち味が生きていた。この作品でもそれが生きていて、何か笑えちゃうというか、微笑ましいというか。それから、本田響矢さんがとてもよかった。
田幸 若い人の反響を見ると、本田さんのファンがすごく増えていて、そこからドラマ視聴に次々と入ってきています。やっぱり入口になれる人をうまくキャスティングするのは大事ですね。
本田さんは朝ドラにも出られていて、いろいろ拝見してはいましたが、世間の人みんなが顔と名前が一致する感じではありませんでした。そういうある意味、手垢のついていない人を二番手に置いて、その役者さんと役柄と作品がうまくマッチすると、こんなにも、恐らくつくり手が予想しないところまで勢いがでるんだなと思いました。
倉田 芳根さんが本田さんに与えた影響が大きいような気がします。私も本田さんは、お顔を見れば、ああ、あれに出ていたなというのがわかるぐらいで、私の中では比較的目新しい俳優さんだったんです。
影山 そういう方が多かったと思います。
倉田 その中で、最初はあまり顔に表情がない。もちろん演技ですけれど「この俳優さん、どんな俳優さんなんだろう」と思っていました。それが、芳根さんと夫婦になって、だんだんいろんな表情を見せてきて、あっ、こんなにすてきな表情ができる俳優さんなんだという気づきが出てきた。
それも多分、芳根さんが相手だったから出せた表情なのかな、というのは勝手な邪推ですけれど、そういうふうに感じさせるだけの力が芳根さんにあると感じました。
田幸 最初は何を聞いても無表情で「問題ないです」と言っていたのに、芳根さんに引っ張られてどんどん表情が柔和になっていく。距離も近くなって、いろいろな感情表現ができるようになって、人間としても成長していく。役者としてのリアルな成長ぶりも、この作品の中で見られる感じがします。
若者のドラマ離れと言われますが、この作品に関しては、20代の方、若い人からすごく反響がありました。私の娘は24歳ですが、娘の周りでもこのドラマにはまっている人が多かった。若い人がリアルタイムでこんなに夢中になるのは大きな功績だと思います。
影山 私は女子大の教員をしていますが、圧倒的人気ドラマでした。他を寄せつけない。学生の方から「キュンキュンします、先生、見てますか」と言ってくる作品は何クールもなかったんじゃないかと思います。
ドラマ離れ、特に恋愛ドラマ離れということが言われて結構たちますが、教え子は「私たちが恋愛ドラマから離れているんじゃなくて、私たちが魅力的に思う恋愛ドラマがないだけ」と言うんです。言い得て妙です。「波うららかに」のようなストーリーを若い人たちは待っていたんだということを強く確認できましたね。
フジテレビは厳しい時代が続いていますが、いい番組で視聴者に訴える図式が徐々にできていると思うんです。抱えている問題は問題として、現場がこうしたすばらしい作品をつくっていることは、僕はメディアでフジに対して厳しく言っていますけれど、評価したいと思います。
「しあわせは食べて寝て待て」の<団地>
影山 「しあわせは食べて寝て待て」(NHK)にいきましょう。
倉田 物語のテンポ感がすきです。日々せわしないじゃないですか、みんな忙しくて時間に追われている。そういう中で、桜井ユキさん演じる主人公は膠原病になってしまい、大手の会社をやめ、小さなところで休みも多めに取りながら働く。給料が減ったので、家賃の安い団地に引っ越して、そこで薬膳と出会い、近所の人とも交流しながら日々を過ごしていく。その様子が描かれるんですが、主人公のような生活を私が今できているかというと、全くできてない。
私は先日、体調を崩して二週間ぐらい休んだんです。思うように働けない時間を持つことになって、何となく主人公に肩入れしてしまいました。いろいろな事情を抱える中で、働くというのはどういうことなのかも結構考えさせられました。
主人公は自身の体調や状況に合わせて、仕事や住む場所を選び取っていきます。私のこれまでの生き方はそうじゃなくて、仕事のペース最優先で、そっちに自分を合わせていました。でも、それとは違う、今の自分を中心に周りの状況を変えていく生き方もあるんだと教えてくれた作品でした。
団地というのがいい舞台です。小泉今日子さんと小林聡美さんの「団地のふたり」(NHKBS・2024)というのがありましたけれど、戦後の昭和時代を感じさせます。ゆったりした時間が流れていそうなイメージそのままの暮らしが描かれていて、ご近所さんとの交流もあって、忙し過ぎる現代人には憧れの生活だと感じました。
田幸 一方、団地への憧れがありつつ、団地の老朽化問題がやっぱり出てくる。いいな、あんなところで老後を過ごしたいなというだけでなく、老朽化、取り壊し、引っ越しの問題に目を向け、おとぎ話にしてしまわない。現実の厳しさもシビアに描いている。優しい温かい世界と、お金や、いろいろ新陳代謝していかざるを得ない厳しい現実を描いているのが、いかにも今のドラマだなと思います。
「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉がこの作品に出てきます。容易に答えの出ない事態に耐え得る能力のことを言うそうです。どう頑張ってもできないことがある時に、それをどう乗り越えるかではなく、できないことはできないまま受け入れて、そこからどうしようかと考える。私たちの日常の中でも、ヒントになる言葉だと感じました。
あと、膠原病の主人公は、はたから見るとどこが悪いのかわからない。外から見ただけではわからない痛みを抱えている人もいるということを覚えておこうと思います。見えない人の痛みにも、できるだけ敏感でありたいと感じました。
影山 ちょっと違う角度で言えば、おとぎ話ではないという点に賛同はしますが、じゃ、現実的なドラマかというとそうでもない。私たち見る者にささやかな夢を見させてくれるというか、本当は無理だけど、そういうのがあるといいよねというささやかな願望。
現実はどうかというと、僕も例外ではないですが、マンション住まいで、お隣りとはできるだけかかわらないように無意識に選択している。その一方で、このドラマのような関係性に憧れている。ないものねだりなんですね。たとえば宮沢氷魚さんみたいなご近所さんは現実にはいなくて、逆にあのトーンでお隣さんが寄ってきたら気持ち悪いですよね。
田幸 怖いですね。
影山 もちろん氷魚君には邪心がなくて、心を許すというか、淡い恋愛感情も、という流れではありましたけれど。
いつも言うことですが、リアリティとおとぎ話とのバランスはすごく大事です。絵空事で薄っぺらいと見る者の心は打たないですから。フィクションだけれど、リアリティがあるということが大事ですね。
中高年が励まされた「続・続・最後から二番目の恋」
影山 「続・続・最後から二番目の恋」(フジ)がよかったです。
テレビは若い人に見てもらってナンボと長らく言われていて、その結果50、60代、私たち世代にエールを送ってくれるドラマが全然ありませんでした。そんな中この作品があらわれて、僕はこれほど月曜9時が楽しみだったことはここしばらくなかったですね。中高年に対して、まだまだ老け込むのは早いよという、甘いのかもしれませんが、温かく強いメッセージをもらったドラマでした。
岡田惠和さんの脚本がすばらしい。ご自身は「岡田の本はいい人ばっかり出てきて薄っぺらい、と言う人がいるんですよ」と自虐しておられますが、岡田さんの、いい人で彩られているドラマは、今でこそ欲しいテイストだと思います。
最終回は一人一人にちゃんといいところがつくってありました。最終回に限らず、ドラマ全体の中でもそれぞれの見せ場をつくる。文字どおりの端役という人はいないんだ、ということですね。
中でも、坂口憲二さんは実際に難病を乗り越え、この作品で11年ぶりに連ドラに復帰しました。そことリンクしたような形で、ドラマの中でも重大な病気を克服する。
さらに(過去作で)坂口さんの主治医を演じていた高橋克明さんが昨年亡くなっているんですが、坂口さんの病との向き合い方を描く中で、高橋さんのエピソードが見事に挿入されていました。亡くなった方への単なるオマージュ、弔いではなく、ドラマの中で大事なポイントのシーンでした。
石田ひかりさんの父親役だった織本順吉さんも亡くなっていますが、この方にもちゃんといい場面が用意されていました。こういうところの一つ一つに、チーム岡田というか、チームワークのすばらしさを感じます。
倉田 中高年が誰しも抱える将来への不安、この先ずっと働けるかとか、そういう不安に対して、そんなことはないと伝えてくれる。そして、中井貴一さんと小泉今日子さんが丁々発止とやりあうシーンが、ただ言い合っているだけなのにすごくおしゃれなんです。すてきな大人像を見せてくれる作品でした。
田幸 一方で彼らは、世代的にはバブル世代かその少し前で「豊かな世代の人たち、いいね」みたいに感じるところもありました。私はまさに氷河期世代なので。ただ、いい時代を生きた人でも、いい時代を知っているからこそ、どんどん厳しくなって落ちていくのを一生懸命支えなければいけない。よかった時代と同じやり方では持ちこたえられない。そこがかなりぶっちゃけて書かれています。
影山 恵まれた人、選ばれし人たちだねという声は僕もよく耳にしました。僕自身はバブル前々夜の入社で、それはもう楽しかったしイケイケでしたけど、気がついてみたら「ちょっと待って。こんなおじいになって」みたいなところはある。その辺の苦悩というか、そのへんもうまく描かれていました。
年を重ねたら老いぼれて引っ込んでいくのではなくて、60歳ぐらいはまだまだ未熟で、人間として仕上がってない。そういう部分を出演者たちが露呈してくれているところに救われました。こんなふうに年を重ねていってもいいんだという免罪符をもらったようです。
田幸 前作のときには、中井さん演じる長倉和平という人が優柔不断で、それほど魅力的に思えなかったんですが、今見るとこういう男性が増えれば世の中やりやすいのにと思いました。
名キャッチャーで、人に対する加害性がない。上の世代の人たちはホモソーシャルな世界観の中で力強く勝ち抜かなければいけなかった。その中で長倉は異質で、困り事を放っておけず、つい引き受けてしまう。受け手で加害性のない男性というのは、こんなにも魅力的に頼もしく見えるんだという、長倉ラブが起こりました。
「対岸の家事」が突きつける現実
田幸 「対岸の家事」(TBS)。この枠はこれまでも家事物をやってきましたけど、ちょっとずつアップデートしている。今回は、今や絶滅危惧種と言われる専業主婦が主人公という点がいいなと思いました。
つまり、仕事、ケア労働としての家事という視点です。これはすごく大事ですし、結局どの道を選んでもなかなか地獄だなと。専業主婦も、兼業のワーキングマザーも、もちろんシングルマザーも地獄じゃんと思ってしまいそうで、結局それは政治の問題だと怒りを感じそうになるんです。
そこにディーン・フジオカさん演じる官僚が出てきて、彼自身イクメンとなり、現場のケア労働に従事している人の大変な状況をじかに見て、その問題意識を政治の方に持ち帰る役目を担う。家事という「ケア労働」に目を向け、個人やご近所、会社などのつながりから政治にまで目を向けさせる複合的な作りが非常にうまいですね。
あと、私が衝撃だったのが、江口のりこさんの憧れの先輩で、バリバリ仕事をしてきた女性の話です。
影山 あれはいい回でしたね。
田幸 はい。組織の中では女性として最高の位置まで来ている。だけれど、私生活よりも仕事を全て優先してきたその人は、会社から女性のロールモデルとしては外されるんです。その一方で「これからの女性のロールモデルはあなただ」と言われるのが、仕事も家庭もどっちも頑張って回している江口さん。
「そんなの聞いてないよ」と思う方がたくさんいると思います。いろんなことを犠牲にして、仕事のために尽くしてきた人を「これからの時代の女性のロールモデルはあなたではない。仕事も家庭もやってきたこっちだよ」とすげかえられる。
女性にとって働きやすい職場だということをアピールするために、私生活を犠牲にした人より、どっちもやってきた人をロールモデルにするというのは、実際に起きている光景なんだろうと思います。そういう組織の残酷さ、社会の変化もしっかり描いていました。私の娘は大手に勤めてるんですが「これって今の本当だよね」と言っていました。
「神説教」と「いつか、ヒーロー」
田幸 「なんで私が神説教」(日テレ)のコンセプトはおもしろかったです。やる気のない教師が主人公で、ほどよい距離感で生徒に接しようとする。「怒るな、褒めるな、相談乗るな」というスタンスの人なんですが、うっかり説教してしまう。でも言っていることはめちゃくちゃ正論で、説教ではなく、最終的には問いかけになっているのが今どきだと思いました。
「御上先生」(TBS・2025)や「宙わたる教室」(NHK・2024)の時にも、今は熱血教師の時代ではなくなっているという話が出ました。まさにそうだなと。この先生も上から押しつけず、問いかけて考えさせる。これが今の教師のあり方の一つのスタンダードになりつつある気がしました。
もう一つ「いつか、ヒーロー」(ABC)が、ヘンな言い方ですが、若干珍味系のドラマでした。
桐谷健太さんの過度な熱量に「何だこれ」と思って見始めたんですが、どういうドラマなのか、なかなかつかめない。桐谷さんがすご過ぎて、そこばかり見てしまうんですが、実は養護施設出身の五人の子どもの物語で、日本社会の構造に切り込んでいく。
違う世代の者同士が共闘したり、自己責任論を批判するところもあって、意外に社会派のドラマだったのかと驚きました。「人生、死ぬまで敗者復活戦」がキャッチコピーで、描こうとしているものは結構現代的でした。
結末に驚いた「あなたを奪ったその日から」
田幸 終わり方に驚いたのが「あなたを奪ったその日から」(カンテレ)です。
幼い娘をアナフィラキシーで亡くした北川景子さん扮する主人公が、その原因となったピザの会社の社長に接近するんですが、その社長の娘は育児放棄で家を出た母を知らず、主人公を母親だと思ってしまう。その子が亡くなった娘と同じくらいの年齢だったことから、連れ去ってしまって育てるんです。
明らかに犯罪なんですが、二人はすごくいい親子関係を築く。それでもラストの方でそれが露見する。これ、普通だったら主人公が罪を償った上で、時がたってから再会するみたいな展開になると思うんです。でもそうじゃない。自分の会社のせいで主人公の娘を死なせ、自分の娘を誘拐された社長の大森南朋さんが、主人公を最終的に許すんです。
育ての親として築いた親子関係を、そっちが本当の親子だとジャッジして娘を返す。主人公の罪を問わない。捕まりもせず、一緒に暮らせるようになる。これは本当はあり得ないし、だめなことなのに、法や倫理ではなく、人情でジャッジする。そして、何より私が驚いたのは、この結末に対して、よかったと感じた視聴者がすごく多かったことなんです。
影山 多かったんですか。
田幸 そうなんです。親子の絆がそのまま維持されたことに「よかったね」と感動している人が多かった。私には、罪は罪として償うという結論しか見えていなかったので、この結末の意外性と、それを喜ぶ視聴者が多かったことに驚いたんです。まあ、今の人の気持ちに沿った現代的な一つの着地点なのかなと思いました。
影山 僕は見ていなくて申し訳ありませんが、幼児誘拐で何年も月日がたってるんですよね。それは刑事事件だから許すも許さないも、捕まるんじゃないですか。
田幸 誘拐はありませんでしたという話になったんです。
影山 そんなことありませんでしたと。
田幸 誘拐はなかった、あそこは実の親子ですと社長が言う。告訴しないでくれと娘に頼み込まれて、その思いに心を打たれて、ということなんです。
影山 意見が分かれるところですね。ここまでおとぎ話にしていいのかと。
田幸 どうかと思わないでもないんですけど、最後まで寄り添って見た人たちには、感動した人が多かったんです。
ドラマが描く「戦争」のリアリティ
田幸 「晴れたらいいね」(テレ東)もおもしろい企画でした。現代の看護師が戦時中のフィリピンにタイムスリップする話ですけど、しっかり従軍看護婦の物語を描いていました。戦後80年の今年、戦争を描く作品を民放がやるのはとてもいいことだったと思います。
倉田 戦争を知らない世代が大多数を占める中で、戦争の怖さ、つらさ、悲惨さをきちんと伝えなくてはなりません。報道によって過去の事実を伝えることも大切ですが、ドラマや小説を通して、それに触れた人の想像力をかき立てることも戦争の抑止に大きく貢献すると思います。
影山 「あんぱん」(NHK)も餓死寸前の場面など、戦争の悲惨さを思い切ってシリアスに描きました。一方で、朝からそういうつらいものは見たくないという声も多かったと聞きます。
しかし、やなせたかしさんの生涯を描くときに、戦争の悲惨さと実体験をきちんと描かないことには、その後の説得力につながらないんです。悲惨なものを正面から描くことはエンターテインメントにとってとても大事です。その意味でテレ東も頑張って放送に結びつけたと思います。
NHKは「あんぱん」で日本人兵士が中国人の男の子に殺されるという回とリンクさせて「チリンの鈴」というアニメを放送しました。やなせさんの原作です。オオカミに母親を殺された子羊の「チリン」が強くなりたいと願ってオオカミに弟子入りする。その結果どんどん強くなって、角まで生えてくる。さらにチリンはオオカミに、かつての仲間を殺すように命じられる。そこでチリンは、ハッと思ってオオカミを殺す。これは「あんぱん」とリンクしています。
田幸 NHKは、力を入れているドラマ放送時に教養番組やドキュメンタリーなど、ジャンルを超えた関連番組も同時期に放送する仕組みを編成が作っていて、うまい手法だと思います。
「あんぱん」ほど長く戦争を描く朝ドラはこれまでありませんでした。でも、戦争編に入ってからの方が視聴率は伸びているそうなんです。
朝から暗いものを見たくないという声はありますが、一方で、戦争をちゃんと描いていることを知って戦争編から見始めた方も結構いる。戦争をしっかり描くことが視聴率を含めて評価されているとなると、暗いものは見たくないというのが覆って、今後の朝ドラに影響を及ぼすんじゃないかと思います。
倉田 「虎に翼」(NHK・2024)がそうでしたが、朝ドラを全然見ない人が「虎に翼」だけは見るということがありました。今回もやなせさんのドラマだからと見始めたんだけど、それだけではなく戦争をしっかり描いていることを評価して見続ける人もいる。ふだんは朝ドラを見ない新しい視聴者を獲得しているように感じます。
「エンジェルフライト」と「地震のあとで」
倉田 「エンジェルフライト」(NHK)は、BSで一回見て、今回地上波で見返しました。海外のテロで家族を亡くしたエピソードのときなどは、何かいろいろ想像力が働き過ぎて号泣してしまったんです。大切な人を亡くすだけでもつらいのに、遺体が海外にあってすぐには対面もできない。そういう時に遺体を連れ帰るという仕事もあるんだという発見もありました。
田幸 死を描いているけれど、死を描くことは結局生きることを描くことなんだと思いました。脚本もよく練られているいい作品でした。
「地震のあとで」(NHK)は、好みが分かれる作品だとは思うんですが、連ドラで描くことのおもしろさがありました。阪神・淡路大震災の後に書かれた村上春樹さんの作品が原作で、震災後の30年間で、ちょっとずつ現代に近づいていく4話です。
その30年間に日本で起こった災厄を描いて、しかもその災厄が起こった直接の場所ではなく、距離の離れたところの人たちの心の揺れを描いているのが非常におもしろい試みでした。
直接被害を受けたわけじゃない、関係のない、遠くにいると思う人でも影響は受ける。ちょっとずつ揺れがつながっていく。この不安感は日本人だからこそ感じるものだと思います。
地震の多い国に住んでいる我々は、常に足元に不安を感じている面があって、そうでない国の人とは人間性や性質に違ってくるところがあるように思います。どうやっても避けられない、いつ来るかわからないグラグラする揺らぎみたいな不安感をどこか抱えながら生きているように思います。
倉田 ドラマ自体は、村上春樹さん原作ということもあって、スッと入り込める感じではなかったんですが、こういう作品をつくり続ける意味はすごくあると思います。
今期、印象に残った俳優は…
影山 「あんぱん」の河合優実さん。戦地に赴く愛する人との別れのシーン。アップになった彼女の、喜怒哀楽でははかれない表情。本当に河合優実を絶賛したい。
田幸 彼女が出てくると、みんながそこに引きつけられてしまう強さがあって、独特の雰囲気がありますね。もう一人言っておきたいのが今田美桜さん。すごくいいです。
影山 そう思います。
田幸 朝ドラのヒロインは基本的に反戦派が多いんです。でも時代を考えれば、軍国主義教育を受けているわけですから、当然そちらの考え方になる。軍国主義を奉じているヒロインを朝ドラは描いてきませんでした。こういうヒロインは、視聴者に好かれにくいんです。
でもそこから戦争体験を経て、大事な人を失ったりしながら変わっていく。そこをせりふではなく、表情で変化を見せるという、非常に難しい役を今田さんは上手に演じています。このヒロインはもっと評価されていいと思います。
倉田 これも「あんぱん」ですが、北村匠海さんがすごくいい。今さらという感じで申し訳ないですが、戦地での演技に引き込まれますし、飢えに苦しむところも、本当に何か食べさせてあげたいと思うくらいの迫真の演技でした。
影山 妻夫木聡さんとのやりとりで、妻夫木さんがワーッと感情を表に出す最後のシーンがありました。北村さんは受けなんですが、いい受けをするなと思いました。存在感のある俳優さんです。
北村さんはインタビューでも自分の演技はほとんど語らないそうです。作品や全体のことは喜んで語るけれど、自分が前にというところはなくて、それが「あんぱん」の演技全体にも出ているように感じます。
<この座談会は2025年7月3日に行われたものです>
<座談会参加者>
影山 貴彦(かげやま・たかひこ)
同志社女子大学メディア創造学科教授 コラムニスト。
毎日放送(MBS)プロデューサーを経て現職。
朝日放送ラジオ番組審議会委員長。
日本笑い学会理事、ギャラクシー賞テレビ部門委員。
著書に「テレビドラマでわかる平成社会風俗史」、「テレビのゆくえ」など。
田幸 和歌子(たこう・わかこ)
1973年、長野県生まれ。出版社、広告制作会社勤務を経て、フリーランスのライターに。役者など著名人インタビューを雑誌、web媒体で行うほか、『日経XWoman ARIA』での連載ほか、テレビ関連のコラムを執筆。著書に『大切なことはみんな朝ドラが教えてくれた』(太田出版)、『脚本家・野木亜紀子の時代』(共著/blueprint)など。
倉田 陶子(くらた・とうこ)
2005年、毎日新聞入社。千葉支局、成田支局、東京本社政治部、生活報道部を経て、大阪本社学芸部で放送・映画・音楽を担当。2023年5月から東京本社デジタル編集本部デジタル編成グループ副部長。2024年4月から学芸部芸能担当デスクを務める。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。
・エアコン「1℃下げる」OR「風量を強にする」どっちが節電?「除湿」はいつ使う?賢いエアコンの使い方【ひるおび】
・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】
・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】

